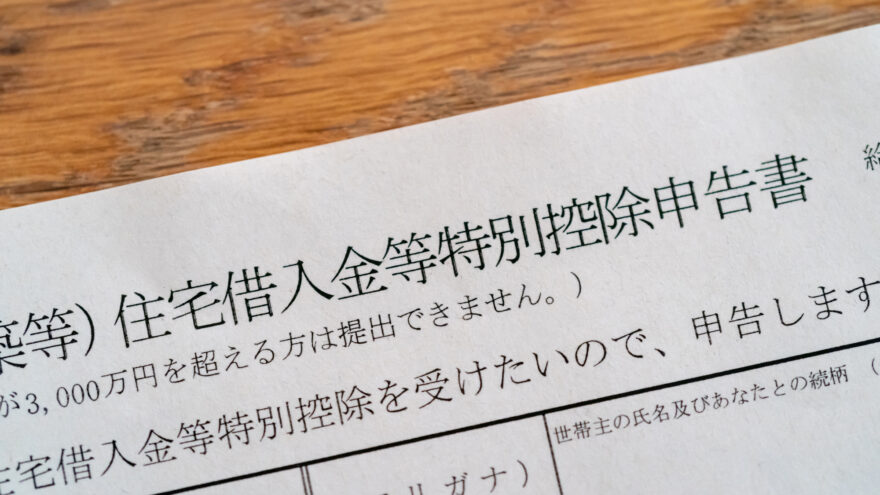住宅ローンのボーナス払いはお得?メリット・デメリットで徹底比較

この記事では、住宅ローンのボーナス払いについて解説します。
住宅ローンのボーナス払いとは、ボーナスが支給された月に通常の毎月返済額に加えて上乗せ分を支払う返済方法です。毎月の負担を抑えて返済期間が短くなるなどのメリットがありますが、総返済額が増加するなどのデメリットもあります。
この記事では、住宅ローンのボーナス払いについて、メリット・デメリットや注意点を解説します。お得になるかをシミュレーションによって検証するので、ボーナス払いの利用を検討している人はぜひこの記事を参考にしてください。
【この記事でわかること】
● 住宅ローンのボーナス払いとは?
● 住宅ローンのボーナス払いを利用するメリット・デメリット
● 住宅ローンのボーナス払いでお得になるのかシミュレーション
● 住宅ローンのボーナス払いを利用する際の注意点
● 住宅ローンのボーナス払いがきついときの対処法
住宅ローンのボーナス払いとは?
住宅ローンのボーナス払いとは、半年ごとのボーナス支給月に毎月の返済にまとまった額を上乗せして返済する方法です。住宅ローンの返済はボーナス払いと毎月同じ額を返済する毎月払いから選択でき、ボーナスで返済できる額の上限は定められている場合がほとんどです。
ここでは、ボーナス払いの詳細を以下2点から解説します。
- ボーナス払いの仕組み
- ボーナス払いにおける返済額の目安
順番に見ていきましょう。
ボーナス払いの仕組み
ボーナス払いでは、借入額を”毎月返済分”と”ボーナス払い分”に分けます。それぞれで返済計画を立てて、それに基づく返済を並行して進めます。
ボーナスが支給された月には、毎月返済額とボーナス払いの金額を合計して返済し、それ以外の月は毎月返済分のみを支払う形です。
ボーナス払いにおける返済額の目安
ボーナス払いを利用する場合、ボーナスで返済できるのは借入額の40%までと定めている金融機関がほとんどです。借入額が3,000万円の場合は、1,200万円をボーナスで払い、残りの1,800万円が毎月返済分となります。
借入額にもよりますが、ボーナス払いでは毎月返済分に10〜30万円を上乗せすることが一般的です。
住宅ローンのボーナス払いを利用するメリット
ここでは、住宅ローンのボーナス払いを利用するメリットを見ていきましょう。
- 毎月の返済額が抑えられる
- 毎月の返済額が同じなら返済期間が短くなる
上記2点を順番に解説します。
毎月の返済額が抑えられる
住宅ローンのボーナス払いを利用すれば、返済額を毎月の返済分とボーナス払い分に分けられ、月々の負担を軽減できます。教育費や車のローンなど他の大きな支払いがある場合でも、月々の住宅ローン返済額を抑えて家計の負担を減らせます。
また、ボーナス支給額が安定している場合、月々の収入から無理に返済額を確保しなくても、年に2回まとまった額を返済すれば資金繰りがスムーズになるでしょう。
毎月の返済額が同じなら返済期間が短くなる
ボーナス払いを利用すれば、返済期間を短縮できます。毎月の返済額はそのままでボーナス支給月に追加返済をすれば、元金の減りが早まりローン完済までの期間が短くなります。
ボーナス払い額を高く設定すれば、その分返済期間を短縮できるでしょう。
住宅ローンのボーナス払いを利用するデメリット
ここでは、住宅ローンのボーナス払いを利用するデメリットを以下2点から解説します。
- 総返済額が大きくなる
- ボーナスの支給額が減少したら負担が大きくなる
順番に見ていきましょう。
総返済額が大きくなる
ボーナス払いでは、元金返済と利息の支払いが年に2回のみであるため、借入金の減りが遅く利息の支払いが多くなります。その結果、毎月返済のみの場合と比べて総返済額が大きくなる傾向があります。
現状では金利が低いため大きな差は出ないといえますが、将来的な金利上昇リスクを考慮すると総返済額が増えるでしょう。ボーナス払いを検討する際には、金利変動の影響や長期的な返済計画をしっかりシミュレーションすることが重要です。
ボーナスの支給額が減少したら負担が大きくなる
ボーナス払いを利用する際は、勤務先の業績や経済状況などの要因から支給額が減少した場合、家計への負担が大きくならないかを考慮する必要があります。
公務員や大企業の正社員なら比較的安定したボーナスを期待できますが、景気や業績の変動によってボーナスが減少したり支給されなかったりするリスクは払拭できません。万が一のケースを避けるためにも、ボーナス払いの比率を高く設定しすぎないことが大切です。
住宅ローンのボーナス払いでお得になるのかシミュレーション
ここでは、住宅ローンのボーナス払いでお得になるか、借入額別にシミュレーションします。シミュレーションの条件は以下のとおりです。
|
【条件】 ● ボーナス払いは借入額の40% ● 元利均等返済 ● 返済金利:0.5% ● 返済年数:35年 |
上記の条件で、3つのケース別にシミュレーションを行います。
- 借入額2,000万円の場合
- 借入額3,000万円の場合
- 借入額4,000万円の場合
順番に見ていきましょう。
借入額2,000万円の場合
借入額2,000万円の場合、返済額は以下のとおりです。
|
ボーナス払いの場合 |
毎月返済のみの場合 |
|
|
借入額のうちボーナス払い |
800万円 |
ー |
|
毎月返済分 |
3.2万円 |
5.2万円 |
|
ボーナス払い(年2回) |
12.5万円 |
ー |
|
総返済額 |
2,182万円 |
2,181万円 |
借入額が2,000万円で金利が低い場合では、総返済額に1万円の違いしかありません。毎月返済額は2万円の差があるので、月々の出費を抑えたい人にはボーナス払いが向いているでしょう。
借入額3,000万円の場合
借入額3,000万円の場合、返済額は以下のとおりです。
|
ボーナス払いの場合 |
毎月返済のみの場合 |
|
|
借入額のうちボーナス払い |
1,200万円 |
ー |
|
毎月返済分 |
4.7万円 |
7.8万円 |
|
ボーナス払い(年2回) |
18.8万円 |
ー |
|
総返済額 |
3,272万円 |
3,271万円 |
借入額が3,000万円の場合でも、ボーナス払いと毎月払いで大きな差はありません。毎月返済額は借入額に比例して大きくなっており、3,000万円の借入額では3万円以上の差がありました。
借入額4,000万円の場合
借入額4,000万円の場合、返済額は以下のとおりです。
|
ボーナス払いの場合 |
毎月返済のみの場合 |
|
|
借入額のうちボーナス払い |
1,600万円 |
ー |
|
毎月返済分 |
6.3万円 |
10.4万円 |
|
ボーナス払い(年2回) |
25万円 |
ー |
|
総返済額 |
4,363万円 |
4,362万円 |
0.5%の低金利では、借入額が4,000万円でもボーナス払いの場合と毎月返済のみの場合で、総返済額に大きな違いはありませんでした。2つの支払方法で毎月返済分に4万円以上の差がありますが、ボーナスで返済する額も大きくなるでしょう。
住宅ローンのボーナス払いを利用する際の注意点
ここでは、ボーナス払いを利用する際の注意点を見ていきましょう。
- 支給額の変動を考慮して返済計画を立てる
- ボーナスで支払う予定の支出を考慮する
- 繰り上げ返済で対応できないか検討する
上記3点を順番に解説します。
支給額の変動を考慮して返済計画を立てる
ボーナス払いを利用する場合、ボーナス支給額が減額されたり、支給されなかったりするなどのリスクがあります。
住宅ローンを組む際には、ボーナスが変動するおそれを考慮することが大切です。勤務先の業績や転職など予測しにくい要因が多く、万が一の事態に備えて返済額に余裕を持たせることや貯蓄を準備しておくことがおすすめです。
ボーナス支給額の変動に備えて柔軟に計画しておくと、安定的に返済できます。
ボーナスで支払う予定の支出を考慮する
ボーナス払いを利用する場合、ボーナスで得た所得を住宅ローンの返済に充てるため、他に回す費用が大幅に減るでしょう。
ボーナスは、貯蓄や生活に必要な費用、生活を豊かにする費用として使うことがほとんどです。
支給されたボーナスを全て住宅ローンに充てるのではなく、自由に使えるお金を確保しておきましょう。充実した生活と返済を両立するためには、余裕のある返済計画を立てておくことが重要です。
繰り上げ返済で対応できないか検討する
繰り上げ返済とは、毎月の返済額とは別にまとまった額を元金の支払いに充てることで、利息を減らして返済期間を短縮する仕組みです。
ボーナス払いとの違いは、ボーナスをどのように使うか自分で選べる点だといえます。
繰り上げ返済を活用すれば、ローン返済の効率を高めながら他の使い道に資金を振り分ける余地が生まれるでしょう。
例えば、旅行や大きな買い物がある月にはローンの支払いをせず、出費が少ない月にまとめて支払えます。インターネット上で手軽に繰り上げ返済ができる金融機関も増えており、計画的な活用が容易になっているといえます。
住宅ローンのボーナス払いがきついときの対処法
ここでは、住宅ローンのボーナス払いがきついと感じるときの対処法を解説します。
- 金融機関に相談する
- 住宅ローンの借り換えを行う
上記2点を順番に解説します。
金融機関に相談する
ボーナス払いを利用している場合、ボーナスが支給されなくなったり、支給額が大幅に減少したりするとローン返済が大きな負担となります。
早めに契約している金融機関に相談し、返済方法の見直しができるか確認しましょう。ボーナス払いを中断し、毎月払いのみに変更できるケースがあります。
ただし、必ずしも返済方法の変更が認められるとはいえないため、毎月の給料の一部をボーナス支払い分として残しておくなどの対策が必要です。
住宅ローンの借り換えを行う
住宅ローンを借り換えることで、支払い方式などの変更が可能です。また、条件が良い金融機関へ借り換えをすれば、金利差による返済負担を軽減できます。
しかし、借り換えをするには新しくローンを契約する必要があるので、諸費用なども考慮したうえで行いましょう。
住宅ローンのボーナス払いに関するよくある質問
ここでは、住宅ローンのボーナス払いに関するよくある質問に回答します。
- ボーナス払いをやめたほうがいいといわれる理由は?
- 住宅ローンのボーナス払いを利用する人の割合は?
疑問の解消にお役立てください。
ボーナス払いをやめたほうがいいといわれる理由は?
ボーナス払いをやめたほうがいいといわれる理由は、総返済額が増える傾向にあるからです。
景気や業績による変動は予測が難しく、長期的に安定して支給される保証はありません。
他にも、ボーナスが支給されなかった場合のリスクが挙げられます。
また、ライフイベントへの対応が難しくなることも懸念材料といえます。ボーナスを住宅ローンに充てることで使途が制限され、教育費や転職後の生活費などの予期せぬ支出に対応できないおそれがあります。
住宅ローンのボーナス払いを利用する人の割合は?
住宅ローンのボーナス払いを利用する人の割合について、公的機関による明確な調査結果は確認できませんでした。
ただし、Web上にある住宅ローンの利用者層へのアンケート結果などから、住宅ローン契約者全体のうち3〜4割程度がボーナス払いを取り入れていると考えられます。
住宅ローンのボーナス払いは支給額の変動を考慮しよう
この記事では、住宅ローンのボーナス払いについて解説しました。
ボーナス払いは毎月の返済負担を抑えられますが、金利によっては大幅に総返済額が増えるなどのデメリットがあります。利用を検討する際には、ボーナス支給額の変動や想定外の支出にも対応できるかなどを考慮しましょう。
ボーナス払いがきついと感じる場合には、金融機関への相談や住宅ローンの借り換えなどがおすすめです。
マイホームを建てる人で資金計画に不安がある場合は、ぜひTATTA!へご相談ください。TATTA!では、月々のローン返済額を抑えながら自由設計の家を建てられます。採用している設備や仕様も性能が高いものが多く、快適に生活できるでしょう。
家づくりに関する相談会も実施しておりますので、ぜひお気軽にお越しください。