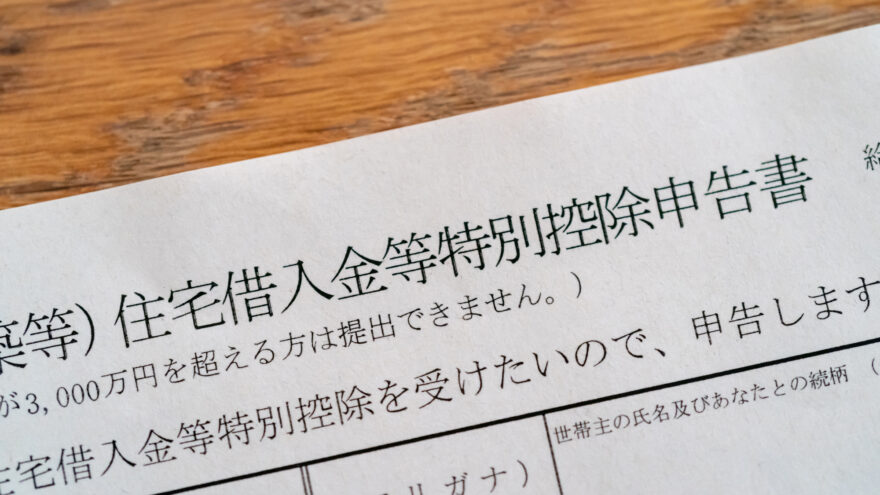住宅ローンのつなぎ融資とは?流れや諸費用・注意点もわかりやすく解説

この記事では、つなぎ融資を利用する場合の流れや、注意点などを解説します。
住宅ローンは、一般的に建物の引渡し時に一括実行されます。注文住宅の場合、土地代金や建築会社に支払う着工金、上棟金などは一時的に自己資金で立て替えなければなりません。
このような立て替えをローンで賄ってくれるのがつなぎ融資です。この記事で解説する内容を押さえながら、つなぎ融資の仕組みを理解していきましょう。
この記事でわかること】
● 住宅ローンのつなぎ融資とは?
● 住宅ローンのつなぎ融資を利用する流れ
● 住宅ローンのつなぎ融資にかかる諸費用
● 住宅ローンのつなぎ融資を利用する際の注意点
● 住宅ローンのつなぎ融資を使わない方法
住宅ローンのつなぎ融資とは?
住宅ローンのつなぎ融資とは、注文住宅が完成するまでの間に発生する支払いに対して、一時的に立替払いをしてくれるローンのことです。
立替払いが必要な理由は、住宅ローンが原則、引渡し時に一括払いとなるからです。
ここからは、つなぎ融資の特徴として以下2点を詳しく見ていきましょう。
- つなぎ融資の仕組み
- つなぎ融資が必要になるケース
順番に解説していきます。
つなぎ融資の仕組み
つなぎ融資を利用することで、引渡し時に住宅ローンが一括実行されるまでの間、必要になる土地代金などを立替払いしてもらえます。
一般的に、引渡し以前に必要になる支払いは以下の通りです。
- 土地代金
- 着工金
- 上棟金
- 引渡し金(住宅ローン実行)
主に、上記4点における住宅ローンが実行されるまでの間に発生した支払いに対して、つなぎ融資金利が発生します。なお、つなぎ融資の金利は住宅ローン一括実行時に精算されます。
つなぎ融資が必要になるケース
自己資金による立替払いが困難な場合に、つなぎ融資を利用します。
住宅ローンが実行されるまでの間、土地代金や着工金などを自己資金で立て替えられれば、つなぎ融資を組む必要はありません。
住宅ローンのつなぎ融資を利用する流れ
つなぎ融資を利用する流れに関して、建築計画の進行に合わせて確認しましょう。
|
期間の目安 (※) |
マイホーム建築の流れ |
つなぎ融資の流れ |
|
3ヶ月 |
● 予算の検討・見極め ● 土地探し |
● なし |
|
4〜7ヶ月目 |
● 建物プラン計画・基本決定 ● 建築会社選定 |
● なし |
|
8ヶ月目 |
● 住宅ローン申込&事前審査 ● 住宅ローン本審査 |
● つなぎ融資申込&事前審査 ● つなぎ融資本審査 |
|
9ヶ月目 |
● 住宅ローン金銭消費貸借契約 ● 土地売買契約 ● 建物金額打ち合わせ・決定 |
● つなぎ融資金銭消費貸借契約 |
|
10ヶ月目 |
● 土地代金支払い ● 建築請負契約 |
● 土地代金:第1回つなぎ融資 |
|
11ヶ月目 |
● 着工 |
● 着工金:第2回つなぎ融資 |
|
12ヶ月目 |
● 建物棟上げ完了 |
● 上棟金:第3回つなぎ融資 |
|
1年2ヶ月目 |
● 建物完成 ● 住宅ローン融資実行 ● 最終金:住宅ローン融資 |
● 引渡し時:つなぎ融資完済、金利精算 |
※期間はあくまで目安
つなぎ融資を利用する場合は、住宅ローンを実行してもらう金融機関がつなぎ融資を取り扱っているかを事前に確認しましょう。
住宅ローンのつなぎ融資にかかる諸費用
つなぎ融資を利用すると、主に以下の諸費用が必要になります。
- 印紙代
- 事務手数料
- 団体信用生命保険料
- 住宅融資保険料
順番に解説していきます。
印紙代
つなぎ融資や金銭消費貸借契約において、必要になる印紙代は以下の通りです。
- 1,000万円を超え5,000万円以下:2万円
- 5,000万円を超え1億円以下:6万円
なお、税金の扱いとなるので消費税はかかりません。
事務手数料
つなぎ融資の事務手数料は、ほとんどの金融機関で11万円(税込)です。
工事の遅延などで返済期日が延長する場合は、改めて事務手数料が必要になります。
団体信用生命保険料
建設中に債務者(ローンを借りている人)が亡くなってしまった場合、土地代金などの支払いでつなぎ融資を組んでいたら、その債務は相続に継承されます。相続した妻や子供たちは、こうした債務を支払わなければなりません。
こうした事態を避けるために、団体信用生命保険(以下団信)が付与されているつなぎ融資(※)を利用しましょう。団信が付与されているつなぎ融資の場合、保険料はつなぎ融資の金利に上乗せされます。
※:つなぎ融資に団信が付与されていない場合は、短期団体信用生命保険や一般の定期生命保険を利用して死亡保障を準備する方法がある
住宅融資保険料
住宅融資保険とは、債務者(ローンを借りている人)が債務不履行となった場合に、その損害を補填する保険のことです。
つなぎ融資であっても、短い期間に不測の事態が起こらないとは限りません。この場合に備えて住宅融資保険に加入し、あらかじめつなぎ融資の金利に上乗せして住宅融資保険料を支払います。
仕組みとしては、住宅金融支援機構が債務不履行となった債務者に代わって、債権者である金融機関に損害の100%or90%を保険金として給付します。
住宅ローンのつなぎ融資を利用する際の注意点
つなぎ融資を利用する際の注意点について解説します。
- 金利が割高になる
- つなぎ融資だけの利用は不可
- 住宅ローン控除が適用されない
- つなぎ融資に対応していない金融機関がある
上記4点を、順番に見ていきましょう。
金利が割高になる
つなぎ融資は、以下の理由から住宅ローンに比べて金利が高めに設定されています。
- 住宅ローンに比べて1年程度と融資期間が短い
- 無担保ローンである
- 団信保険料や住宅融資保険料が上乗せされる
実質の金利は金融機関によって異なるものの、2〜4%程度のところがほとんどです。
なお、建物が完成するまでの間は金利分のみを返済して、引渡し時に実行された住宅ローン融資でつなぎ融資を精算するのが一般的です。
つなぎ融資だけの利用は不可
つなぎ融資を受けるためには、以下の2つの条件を満たさなければなりません。
- 住宅ローンと同時につなぎ融資も事前審査・本審査を受け、金融機関の内諾を得る
- 建物の完成後に、つなぎ融資を同じ金融機関の住宅ローンで一括返済する
このように、つなぎ融資は住宅ローンの本融資とセットで契約する場合がほとんどです。
住宅ローン控除が適用されない
つなぎ融資の借入期間は通常1年間のため、住宅ローン控除の借入期間10年以上の適用要件を満たせず、住宅ローン控除を受けられません。
年末など、物件の引渡しを受け住宅ローンが実行されるまでの間に年が代わってしまうような場合は、住宅ローン控除の適用が翌年からになります。
つなぎ融資に対応していない金融機関がある
そもそも、つなぎ融資の取り扱いがない金融機関も存在します。
ネット銀行などは住宅ローン金利が安い反面、つなぎ融資を取り扱っていないケースも少なくありません。
したがって、相談している金融機関に取り扱いがない場合は、建築会社やハウスメーカーに相談しましょう。建築会社やハウスメーカーが金融機関と提携すれば、つなぎ融資の利用が可能になる場合もあります。
住宅ローンのつなぎ融資を実際にシミュレーション
ここでは、住宅ローンのつなぎ融資を、実際にシミュレーションしてみましょう。
以下の通り条件を設定しながら解説していきます。
|
<条件> ● 土地代金:1,000万円(諸費用:別途200万円) ● 建物代金:1,650万円(税込) ● つなぎ融資金利:2% ● つなぎ融資の手数料:13万円(融資事務手数料11万円+印紙税2万円) |
上記を条件に設定した場合、支払い項目や金額、支払い方法は以下の通りです。
|
支払い項目 |
金額 |
支払い方法 |
|
土地契約時の諸費用 |
200万円 |
自己資金 |
|
土地代金 |
1,000万円 |
つなぎ融資 |
|
契約金 |
150万円 |
自己資金 |
|
着工金 |
500万円 |
つなぎ融資 |
|
上棟金 |
500万円 |
つなぎ融資 |
|
引渡し金 |
500万円 |
住宅ローン |
上記の通り、土地代金・着工金・上棟金の支払い時につなぎ融資を利用します。なお、つなぎ融資の金利は、以下の計算式で算出できます。
|
<つなぎ融資における金利の計算方法> ● 借入額×金利÷365(日)×完成までの日数(日) |
上記を踏まえて、ここからはつなぎ融資を利用した場合の土地代金や着工金、上棟金における利息の金額を算出していきましょう。
なお、日数の計算にあたり土地契約から引渡しまで、それぞれ以下の日程に支払うと仮定します。
|
支払い日 |
支払い項目 |
|
令和4年3月30日 |
土地契約時の諸費用 |
|
令和4年4月30日 |
土地代金 |
|
令和4年5月1日 |
契約金 |
|
令和4年6月1日 |
着工金 |
|
令和4年7月31日 |
上棟金 |
|
令和4年9月30日 |
引渡し金 |
この場合、それぞれ利息の計算方法は以下の通りです。
|
<土地代金における利息の計算> ● 1,000万円×2%÷365(日)×154(日)=8万4,383円(1) <着工金における利息の計算> ● 500万円×2%÷365(日)×122(日)=3万3,424円(2) <上棟金における利息の計算> ● 500万円×2%÷365(日)×62(日)=1万6,986円(3) |
上記の計算式から、各金利の合計は「(1)+(2)+(3)=13万4,793円」となります。
そして、今回の条件設定では、手数料と利息を合わせると約26万4,793円の費用が発生するとわかりました。
ただし、上記に加えて土地と建物代金の約1%に相当する金額が、住宅ローンとは別に必要になることを理解しておきましょう。なお、今回の条件設定では金利を2%としましたが、3〜4%になると負担額がさらに大きくなります。
住宅ローンのつなぎ融資を使わない方法
自己資金・つなぎ融資以外で、土地代金や着工金などを支払う方法について解説します。
- 住宅ローンの分割融資を利用する
- 親族や親戚からの贈与で自己資金を増やす
順番に見ていきましょう。
住宅ローンの分割融資を利用する
住宅ローンの分割融資とは、1本の住宅ローンに対して引渡し時の1回ではなく、複数回に分けて実行される融資です。
住宅ローン金利が適用されるので、つなぎ融資よりも金利負担を抑えられます。つなぎ融資では実現できなかった住宅ローン控除が適用できるのも、分割融資のメリットの1つです。
ただし、つなぎ融資では登記費用がかからない点に比べて、分割融資の場合は事前に抵当権を設定するため登記費用がかかります。また、融資実行のたびに手数料が発生するので注意しましょう。
住宅ローンの分割実行ができる金融機関は限られているので、分割実行を検討したい場合は事前にチェックが必要です。
親族や親戚からの贈与で自己資金を増やす
「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」措置を利用して、自己資金を増やす方法があります。具体的には、以下の通りです。
<住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税とは>
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、住宅取得資金の一部について父母・祖父母から受けた贈与において、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる制度のことです。
<受贈者(自宅を建てる人)の非課税限度額>
|
省エネ住宅 |
省エネ以外の住宅 |
|
|
令和4年1月1日から |
1,000万円 |
500万円 |
夫婦双方の両親・祖父母から贈与を受けた場合、最大2,000万円まで(省エネ住宅の場合)非課税になります。
この制度を利用すれば、贈与の額により500〜2,000万円の自己資金が用意できることになるので、該当者はなるべく利用しましょう。
住宅取得資金の贈与は、相続開始前3年以内の相続税加算の適用もなく500〜1,000万円を課税対象から外せるので、相続対策としても効果的です。
住宅取得資金の贈与を利用する場合は、以下の2点を忘れずに実行しましょう。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること
- 非課税であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告すること
万が一、上記を忘れると課税されるケースもあるので注意が必要です。
住宅ローンのつなぎ融資に関するよくある質問
最後に、住宅ローンのつなぎ融資に関するよくある質問を紹介します。
- 注文住宅のつなぎ融資は不要?
- つなぎ融資ができるネット銀行の一覧は?
順番に回答していきます。
注文住宅のつなぎ融資は不要?
土地代金や着工金などを立て替えられれば、つなぎ融資は必要ありません。
しかし、大きな金額の支払いを自己資金で立て替えられる人は少ないので、ほとんどの場合つなぎ融資の検討が必要になります。
つなぎ融資ができるネット銀行の一覧は?
2023年1月現在、つなぎ融資が利用できるネット銀行は主に以下の通りです。
|
金融機関名 |
条件 |
|
最大3分割まで |
|
|
土地代金のみ |
|
|
最大4分割まで |
|
|
最大2分割まで |
|
|
– |
なお、ソニー銀行などは、自行でつなぎ融資を取り扱っていないものの、住宅つなぎローン(アプラスブリッジローン)によって利用できるケースがあります。
住宅ローンのつなぎ融資は注意点を押さえて上手に活用
住宅ローンのつなぎ融資は、土地代金などのまとまった大きな金額を、一時的に支払うときに利用できる便利な融資です。
ただし、住宅ローンよりも金利が高く、住宅ローン控除が翌年にずれ込むなどのデメリットがあるので注意が必要です。
したがって、立て替えできる自己資金があれば、無理のない範囲で自己資金を用意しましょう。
グッドリビングは、1980年の創業以来40年以上にわたって「高品質の住宅を低価格で」をモットーに、お客様に最適なプランを提案してきました。
資金計画の相談も承っているので、住宅ローンやつなぎ融資でお悩みの場合は、ぜひグッドリビングへお問い合わせください。