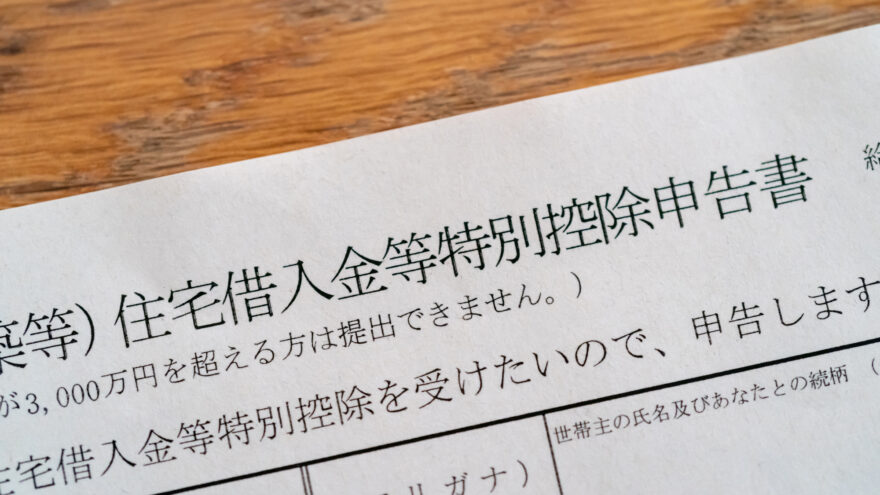住宅ローンに諸費用は組み込み可能?メリット・デメリットも解説

この記事では、住宅購入の諸費用は住宅ローンに組み込めるのかについて解説します。
結論、住宅購入の諸費用は住宅ローンに組み込めるものとできないものがあります。住宅ローンに諸費用を組み込むことにはメリットだけでなくデメリットもあるため、注意が必要です。
事前にどれくらいの自己資金を用意しておくかを把握するためにも、諸費用の内訳を知っておいたほうが良いでしょう。
そこで、この記事では住宅ローンに組み込める諸費用と組み込めない諸費用の違い、組み込むことのメリット・デメリットについて解説します。
資金計画でお悩みの人は、ぜひ最後までお読みください。
【この記事でわかること】
・住宅購入の諸費用とは?
・住宅ローンに諸費用は組み込み可能?
・住宅ローンに諸費用を組み込みするメリット・デメリット
・住宅ローンへの組み込み以外で諸費用を支払う方法
・住宅ローンに諸費用を組み込むときの注意点
・住宅ローンの諸費用組み込みでおすすめの銀行
\オンライン相談も好評/
相談だけでもOK!
家づくりのプロが、あなたの疑問や不安に個別でお答えします。
そもそも住宅購入の諸費用とは?
住宅ローンに諸費用を組み込むべきかどうかを検討する際には、そもそも住宅購入における諸費用の意味を知っておくことが必要です。
諸費用には建物にかかる諸費用と住宅ローンにかかる諸費用があります。それぞれの諸費用について解説していきます。
- 建物にかかる諸費用
- 住宅ローンにかかる諸費用
- 諸費用の平均目安
- 諸費用を支払うタイミング
建物にかかる諸費用
建物にかかる諸費用はハウスメーカーや建築プラン、建てる土地によって多少の違いはありますが、一般的には次のような内容になります。
|
諸費用の内容 |
費用の目安 |
|
ライフライン引込工事費用 |
100〜150万円 |
|
地盤調査費用 |
10万円前後 |
|
地盤改良費用 |
150〜200万円(ゼロの場合もある) |
|
造成費用 |
200万円前後(ゼロの場合もある) |
|
外構費用 |
200万円前後 |
|
建築申請などの申請費用や各種税金 |
50万円前後 |
建物の諸費用で必ずかかるのが、ライフライン引込工事費用です。上水と下水、さらにガスを使うのであればガス管の引込工事が必要となり、100〜150万円程度の費用が一般的です。
また、どのハウスメーカーであっても地盤調査は実施することになります。地盤改良が必要な場合は150〜200万円の地盤改良費がかかります。ただし、調査の結果地盤改良が不要だと判明した場合は地盤改良費は不要です。
諸費用がゼロになる可能性がある項目として造成費用もあります。フラットな土地であれば造成することなく建築可能です。
ほかにもフェンスや庭、駐車場を造作するための外構費用や各種申請費用、税金などが建物の諸費用となります。
住宅ローンにかかる諸費用
住宅ローンを組む際には”事務手数料”と”保証料”がかかります。費用の目安は以下の通りです。
|
諸費用の内容 |
費用の目安 |
|
住宅ローン事務手数料 |
● 定額の場合は3〜33万円 ● 定率の場合は借入額×2.2% |
|
住宅ローン保証料 |
● 借入額1000万円あたり20万円前後 |
※住宅ローン事務手数料は定額か定率かで異なる
事務手数料とは金融機関が住宅ローンの申請を手続きする際にかかる費用で、保証料は保証会社に支払う保証金です。
住宅ローン事務手数料は、借入額によらず金額が一定の”定額型”と、借入額に連動して金額が変動する”定率型”があります。
事務手数料と保証料は、借入金額や借入する人の属性によって変わることがあるので、検討している金融機関に確認することをおすすめします。
諸費用の平均目安
住宅購入では、物件価格以外にも諸費用がかかります。仲介手数料や登記費用、住宅ローン手数料、火災保険料などを指し、購入価格の約3〜8%が目安です。
物件の種類によって諸費用が物件価格で占める割合は異なり、 新築では購入価格の約3〜5%、中古物件の場合には購入価格の約6〜8%が目安とされています。
融資元の金融機関や、個別の取引条件により変動幅がある点に注意が必要です。
たとえば、新築5,000万円の物件なら150〜250万円程度が必要になります。住宅を購入する際には見落としがちな費用ですが、計画的に備えておけば安心して支払えるでしょう。
諸費用を支払うタイミング
住宅購入の際に発生する諸費用は、売買契約時・決済と引渡し時・引渡し後の3つのタイミングに分けて支払います。原則、現金払いになることが多い点に注意が必要です。
諸費用を支払うタイミングをまとめた表は、以下のとおりです。
|
タイミング |
詳細 |
|
売買契約時 |
・印紙税(1000万円を超え5000万円以下の場合、税額は1万円 ※売買契約書に貼付け ・仲介手数料の半金(売買代金×3%+6万円+消費税10%を上限) |
|
決済と引渡し時 |
・印紙税(借入額が1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円) ※ローン契約書に貼付け ・登記費用(登録免許税、司法書士報酬) ・ローン借入費用(事務手数料、保証料、火災保険料など) ・仲介手数料の半金 ・水道負担金(新築一戸建て) ・固定資産税・都市計画税の精算金 |
|
引渡し後 |
・不動産取得税(引き渡しの半年~1年半後に都道府県から納税通知書が送付) ・引越し代や家具購入費用など |
契約時には、諸費用の他に手付金も支払う必要があります。手付金は売買契約を結ぶ際に必要なお金で、住宅ローンの融資前に支払うため、あらかじめ自己資金で準備しておきましょう。
住宅ローンに諸費用は組み込み可能?
結論として、全ての諸費用を住宅ローンに組み込めるわけではなく項目によって異なります。
- 組み込みできる諸費用
- 組み込みできない諸費用
組み込みできる諸費用
住宅ローンに組み込める諸費用として、主に以下の項目があります。
- 上下水引込工事費用
- 地盤調査費用
- 地盤改良費用
- 造成費用
- 外構費用
- 印紙税
- 住宅ローン手数料と保証料
- 登記費用
- 仲介手数料
印紙税は、不動産売買契約書や請負契約書、金消契約書に貼付する印紙の代金です。
また、登記費用は所有権移転登記費用や建物の保存登記、司法書士への報酬などで、仲介手数料は不動産仲介業者へ支払う報酬です。
基本的には、土地を購入し建物を建てるために必要となる諸費用は組み込めます。ただし、一部の税金や家を建てた後にかかる費用は組み込みできないことが多いといえます。
組み込みできない諸費用
住宅ローンの諸費用に組み込みできない費用には、次の内容があります。
- 不動産取得税
- 固定資産税及び都市計画税
- 家具や家電の購入費用、引っ越し費用
不動産取得税は、不動産を取得した翌年度に支払う税金で、固定資産税や都市計画税は不動産を所有している間支払い続ける税金です。家を建て入居した後にかかるため、住宅ローンに組み込むことはできません。
また、家具や家電の購入費用、引っ越し費用も住宅ローンには組み込めないので注意が必要です。
住宅ローンに諸費用を組み込みするメリット
住宅ローンに諸費用を組み込むことには、以下のメリットがあります。
- 初期費用の負担を軽減できる可能性がある
- 諸費用を組み込んだ場合にも住宅ローン控除(減税)が適用される
- お金を手元に確保できる
- 返済を一本化できる
これから注文住宅の資金計画を立てる人はぜひ参考にしてください。
初期費用の負担を軽減できる可能性がある
住宅ローンに諸費用を組み込む最大のメリットは、自己資金による初期費用の負担を軽減できる点です。登記費用や火災保険料、仲介手数料などは数十万円〜100万円以上かかることもあるため、現金での支払いが難しい場合に有効といえます。
諸費用をローンに含めれば手元資金を温存できるので、引越し後の生活費や家具購入費などに充てる余裕もが生まれるのが嬉しいポイントです。
ただし、返済額は増えるため、計画的に利用するようにしましょう。
諸費用を組み込んだ場合にも住宅ローン控除(減税)が適用される
住宅ローンを組むと住宅ローン控除が適用され、諸費用を組み込んだ場合にも年末のローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除されます。
ただし、控除対象は住宅取得費に限られ、火災保険や引越し費用、家具・家電代などの諸費用は含まれない場合があります。
諸費用を含めて借入する場合、借入額が多くなりますが、諸費用は控除の対象外となることもある点に注意が必要です。
お金を手元に確保できる
住宅ローンに諸費用を組み込む場合、自己資金を用意したりフリーローンを組んだりする必要がないため、手元にお金を残せます。
万が一の出費に対応しやすくなり、安心して生活できるでしょう。どのくらいの貯金があれば安心なのか家族で話し合い、安心できるラインよりも多くのお金を自己資金として用意しておくことがポイントです。
住宅ローンに諸費用を組み込むことで、手元資金の余裕が生まれ、精神的にも余裕が生まれるメリットがあります。
返済を一本化できる
住宅ローンに諸費用を組み込むことで月々の返済が一本化されるため、管理の手間がかかりません。
逆に、フリーローンを他の金融機関で組むと返済先が分散され、残高などの管理が複雑になってしまうでしょう。
管理しやすい点も、住宅ローンに諸費用を組み込むメリットだといえます。
住宅ローンに諸費用を組み込みするデメリット
ここでは、住宅ローンに諸費用を組み込むデメリットを解説します。
- 毎月の返済額が高くなる場合がある
- 総返済額が高くなる
毎月の返済額が高くなる場合がある
諸費用を組み込むことで住宅ローン控除額が増える理由は、返済額が増えているからです。
毎月の返済額も増えることになり、住宅ローン控除の適用期間が終了してしまうと負担が増加するデメリットがあります。
住宅ローンの返済額は、住宅ローン控除と月々返済額とのバランスが重要となります。
総返済額が高くなる
住宅ローンの借入額が増えると、金融機関に支払う利息も増えます。総返済額が諸費用と利息の分だけ増えてしまい、老後の生活に影響が出てしまうことも考えられます。
目先の貯金や住宅ローン控除だけでなく老後も踏まえて資金計画を立てることが重要です。
住宅ローンへの組み込み以外で諸費用を支払う方法
前述のとおり、全ての諸費用が住宅ローンに組み込めるわけではありません。そのため、住宅ローン以外の方法で諸費用を支払う準備をすることになります。
ここでは、住宅ローンを利用せずに諸費用を支払う方法について解説します。
- 自己資金で支払う
- 諸費用ローンで支払う
自己資金で支払う
住宅ローンに諸費用を組み込まず、自己資金で支払う方法もあります。借入額が増えないため、金利上昇リスクを抑えられるのがメリットです。
国土交通省の令和6年度住宅市場動向調査によると、令和6年度における注文住宅の住宅建築資金の自己資金は1,825万円です。令和2年度は848万円でしたが年々増加傾向にあります。
自己資金が十分でなければ諸費用の負担が重くなるため、無理のない範囲で準備し、資金計画をしっかり立てることが重要です。
※参考:令和6年度 住宅市場動向調査報告書(P117)|国土交通省(住宅局)
諸費用ローンで支払う
住宅購入時に発生する諸費用は、通常の住宅ローンに上乗せして借入できる場合があります。
諸費用専用のローンを提供している金融機関もあり、火災保険料や保証料、登録免許税、引越し費用などで利用することが可能です。静岡県にも、対応している金融機関が存在します。
資金繰りの選択肢として有効ですが、無理のない返済計画を立てたうえで利用をしましょう。
\オンライン相談も好評/
相談だけでもOK!
家づくりのプロが、あなたの疑問や不安に個別でお答えします。
住宅ローンに諸費用を組み込むときの注意点
ここでは、住宅ローンに諸費用を組み込むときの注意点について解説します。
- ローン審査が厳しくなる可能性がある
- 金利が高くなる可能性がある
- 金融機関によっては組み込めない場合がある
住宅ローンに諸費用を組み込むと初期費用を抑えられますが、借入額や返済負担が増えるため利用する際は注意が必要です。
ローン審査が厳しくなる可能性がある
住宅ローンに諸費用を組み込む場合は、ローン審査が厳しくなる可能性があります。なぜなら、諸費用を組み込むと借入総額が増加し、年収に対する返済負担率も上昇するからです。
金融機関は、返済負担率が高くなるほどリスクが大きいと判断するので、審査を通過するハードルが上がってしまうでしょう。
借入額が物件価格を超えるオーバーローンとなる場合は、審査基準が厳格になるため、希望額が借りられなかったり、適用金利が上がったりする可能性がある点に留意してください。
金利が高くなる可能性がある
諸費用を住宅ローンに組み込む場合や、諸費用専用ローンを利用する場合、通常の住宅ローンよりも金利が高く設定されるケースがあります。
特に、諸費用ローンは低金利な住宅ローンに組み込む場合より金利が高く、利息の負担が大きくなる点に注意してください。
金融機関によっては住宅ローンの金利優遇が受けにくくなる可能性もあるため、事前に融資条件をしっかり確認しておくことが必要です。
金融機関によっては組み込めない場合がある
住宅ローンに諸費用を組み込めるかどうかは、金融機関ごとの方針によって異なります。一部の金融機関では物件価格分までしか融資できず、諸費用は自己資金で賄うケースもあります。
その場合、引越し費用や家具購入費などは対象外となるため、住宅ローンの申込前に諸費用の取り扱いについて金融機関に確認するようにしましょう。
住宅ローンの諸費用組み込みでおすすめの銀行
ここでは、住宅ローンに諸費用を組み込める銀行の中から、3つの銀行について解説します。それぞれの特徴は以下の通りです。
|
金融機関 |
特徴 |
|
auじぶん銀行 |
● 複数サイトで顧客満足度1位 ● 最低金利0.780%〜 ● 充実した団信ラインナップ |
|
住信SBIネット銀行 |
● 保証料、繰り上げ返済手数料が無料 ● 最低金利0.698%〜 ● 全疾病団信がある |
|
SBI新生銀行 |
● 変動金利(半年型)0.660%〜 ● ガン団信の金利上乗せが0.1% ● インターネットと対面で面談可能 |
※2025年10月現在
auじぶん銀行
auじぶん銀行の特徴は、圧倒的な低金利です。
変動金利で0.780は他の金融機関よりも安く、月々の返済額を抑えたい人におすすめです。低金利が評価され、多くの調査サイトで顧客満足度1位となりました。
また、債務者が万が一死亡や重大な障害状態になった際に備える、団体信用生命保険のラインナップが充実している点も、auじぶん銀行の魅力です。
auじぶん銀行は低金利と充実した団信を両立しており、特に変動金利を検討する方に人気が高いと言えます。
住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行の大きな特徴は、団体信用生命保険に全疾病という商品があることです。ほぼ全ての病気やケガに対応しており、将来のリスクに対して幅広くカバーすることが可能です。
また、保証料や繰上手数料の一部が無料という特徴もあります。住信SBIネット銀行は、将来の病気やケガを懸念する人に人気の銀行といえます。
保証料と繰り上げ手数料の無料制度は、諸費用や将来の返済負担を抑えたい利用者にとって大きなメリットとなります。
SBI新生銀行
SBI新生銀行(旧・新生銀行)では、住宅ローン申込み時に諸費用(事務手数料・保証料・登記関連費用・火災保険料など)を借入金額に含めて借りることが可能です。
事務手数料は借入金額の2.2%(税込)が基本となっており、これも含めて融資を申請できます。 家具や家電、引越し費用などもまるごとサポートできるため、手持ち資金が少ない人が活用できるローンです。
ただし、諸費用込みで借りたい金額すべてが承認されるわけではなく、審査内容に応じて融資できる上限が決まる点に注意しましょう。
住宅ローンに諸費用を組み込むかは慎重に判断しよう
住宅ローンに諸費用を組み込むべきかどうかを悩む人は多く、注文住宅を建てる上でも重要なポイントです。組み込みについてわからないことがあれば、金融機関やハウスメーカーなどの専門家に相談するのがおすすめです。
TATTA!は、静岡県を中心にワンプライスの注文住宅を取り扱っています。家づくりに関する悩みごとに応じ、お客様に合った資金計画を提案しています。提携している金融機関から金利プランや団体信用生命保険の商品説明を受けることも可能です。
住宅ローンに関して相談したい人は、ぜひTATTA!にお問い合わせください。