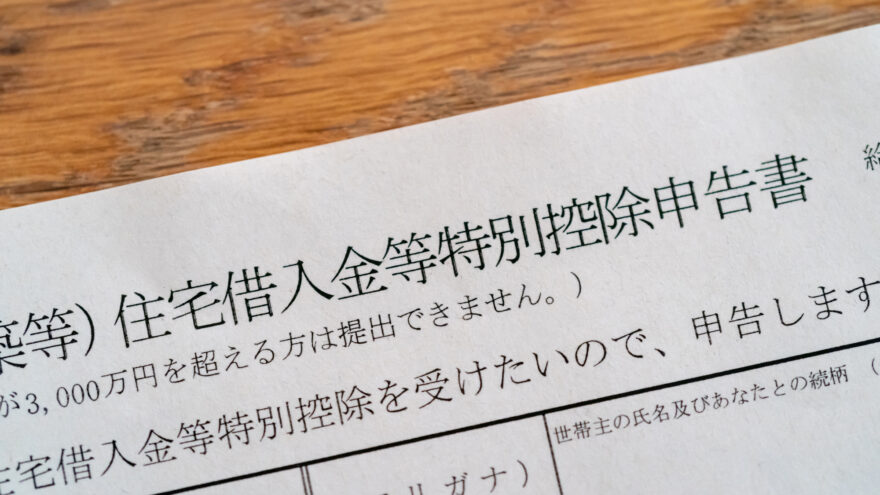ツーバイフォー工法(2×4)とは?メリット・デメリットや注意点も解説

メリット・デメリットや注意点も解説
ツーバイフォー工法(2×4)は壁・床・天井をパネル化し、六面体で支える木造建築の工法で、日本の住宅にも広く普及しています。
耐震性・耐火性・気密性に優れ、工期が短く品質も安定しやすいのがメリットですが、間取りやリフォームの自由度が低い点はデメリットといえます。
この記事では、ツーバイフォー工法の特徴やメリット・デメリットや注意点についてわかりやすく解説します。
この記事でわかること】
・ツーバイフォー工法(2×4)とは?
・ツーバイフォー工法(2×4)のメリット・デメリット
・ツーバイフォー工法(2×4)の施工事例
ツーバイフォー工法(2×4)とは?
はじめに、ツーバイフォー工法(2×4)の基礎知識について解説します。
- 在来工法との違い
- ツーバイシックス(2×6)との違い
在来工法との違い
ツーバイフォー工法(2×4)は柱や梁を使わず、2×4材(3.8cm×8.9cm)の木材に構造用合板を貼り合わせてパネル化し、床・壁・天井を組み合わせて箱型にする工法です。釘で固定していくため施工が均一化しやすく、耐震性や気密・断熱性に優れた住宅を効率的に建てられます。
一方、在来工法は柱や梁など垂直な木材で組み立てる軸組工法で、9cm角の無垢材や集成材を柱に使用します。長い歴史を持ち、日本の木造住宅の約8割に採用されている方法です。
柱と梁が基本構造のため、自由な間取りを実現できるでしょう。つまり、2×4は安定した性能、在来工法は間取りの柔軟性に強みがあるといえます。
ツーバイシックス(2×6)との違い
ツーバイフォー工法(2×4)とツーバイシックス工法(2×6)の大きな違いは、使用する木材の厚みにあります。
2×6は2×4に比べ壁内寸法が約1.6倍となり、分厚い断熱材を充填できるため、断熱性能・気密性能・遮音性能が大幅に向上するのがメリットです。また、構造材自体が大きいため建物の強度も高まり、より安心で快適な住環境を実現できるでしょう。
一方、木材が大きく重いため施工に手間がかかり、必要な部材も増えることから建築コストが高くなる点がデメリットです。
2×4はコストと施工性に優れ、2×6は快適性と耐久性に優れる点に違いがあります。
ツーバイフォー工法(2×4)のメリット
ここでは、ツーバイフォー工法(2×4)のメリットを見ていきましょう。
- 耐震性に優れている
- 耐火性に優れている
- 遮音性に優れている
- 耐久性に優れている
- 気密性・省エネルギー性に優れている
- 品質に差が生じにくい
- 施工期間が短い傾向にある
耐震性に優れている
ツーバイフォー工法は、壁・床・天井をパネル化し六面体の箱型構造を形成するため、地震の揺れを建物全体でバランスよく受け止めることができます。
点や線で支える在来工法に比べ、力を「面」で分散するため耐震性が高いのが大きな特徴です。
横揺れやねじれにも強い安定した構造であるため、繰り返しの余震にも耐えやすく、安心して長く暮らせる住まいを実現できるでしょう。
耐火性に優れている
ツーバイフォー工法は、木造でありながら耐火性に優れているのが特長です。厚みのある構造材は火災時に表面が炭化して内部を守るため、燃え広がりにくい性質があります。
また、床や壁に組み込まれた枠組材がファイヤーストップ材として働き、火の通り道を遮断します。
この仕組みにより「外部から燃えにくい」「火が他室へ広がりにくい」「延焼を遅らせる」という基準を満たし、多くの住宅が特別な対策をせず省令準耐火構造に認定されます。その結果、火災保険料も一般木造より安くなるのがメリットです。
遮音性に優れている
ツーバイフォー住宅は気密性の高い構造のため、遮音性に優れています。
床根太に天井材を直貼りせず、空気層を挟んだうえで、別に天井根太を設けて遮音性の高い石膏ボードを貼ることで効果を高められます。
壁や天井には吸音性に優れた繊維系グラスウールが断熱材として使用されるので、さらに遮音性が高まるでしょう。
近年、上下階の遮音性をさらに高めるために、上階の床材の下に高比重遮音マットを敷くケースも見られます。
生活音を抑える工夫として、階段や水回りを寝室から離して配置することや、床仕上げにカーペットを採用することも有効です。
耐久性に優れている
ツーバイフォー住宅は、耐久性に優れているのも大きな特長です。
使用する構造材はJAS規格に基づいた含水率19%以下の乾燥材で、反りや割れが起きにくく長期的に安定します。
さらに、床下の土壌には防蟻剤を塗布し、防湿シートで水蒸気を遮断することで湿気やシロアリ被害を防ぎます。
加えて、1階床組や立ち上がり部分の木材には防腐・防蟻剤を塗布する二重三重の対策が施されており、木造住宅でありながら長期間安心して暮らせる耐久性を実現しています。
気密性・省エネルギー性に優れている
ツーバイフォー住宅は、気密性・省エネルギー性に優れており、快適かつ経済的な暮らしを実現できるのもメリットです。
構造体には熱伝導率の低い木材を使用し、外壁は大壁構造とすることで枠組材の間に断熱材を充填することで、室内外の温度の移動が少ない住まいをつくります。
さらに外壁は構造用面材と石膏ボードで挟まれ、天井や床内部にも断熱材を敷き詰めることで建物全体を断熱材で覆います。
これにより冷暖房効率が高まり、省エネ・電気代削減にもつながるでしょう。
品質に差が生じにくい
ツーバイフォー住宅は、施工品質に差が生じにくい点も大きなメリットです。
使用する木材や釘・金物のサイズ、施工手順まで細かく規定されているため、現場や職人ごとの経験や技量に左右されにくく、安定した仕上がりが実現します。
また、構造材は工場で事前に加工されることが多く、現場では組み立て作業が中心となるため精度が高まりやすいのも特長です。その結果、品質の均一性が確保され、長期的に安心して住める住宅を提供できる工法といえます。
施工期間が短い傾向にある
ツーバイフォー住宅の工期は、3〜4ヶ月程度と短い傾向にあります。なぜなら、工場で大半の部材を製作し、現場は組み立て工程に特化しているからです。
そのため天候の影響を受けにくく、予定通りに工事が進みやすいため、工期が短縮されることで人件費や仮設費などのコストも抑えられます。
建築業者や職人の技量に左右されにくく安定した品質が確保されやすいのも、ツーバイフォー工法が持つ魅力の1つといえるでしょう。
ツーバイフォー工法(2×4)のデメリット
ツーバイフォー工法(2×4)には多くのメリットがある一方、以下のようなデメリットも存在します。
- 間取りの自由度が低い傾向にある
- リフォームの自由度が低い傾向にある
- 構造体の建築コストを削れない
間取りの自由度が低い傾向にある
ツーバイフォー工法は壁で建物を支える構造のため、在来工法に比べて間取りの自由度がやや低い点がデメリットといえます。たとえば、壁を取り払って大開口の窓を設けたり、広いワンフロア空間をつくることは難しいでしょう。
また、室内の壁も耐力壁として機能しているため、リフォーム時に間取りを変更しようとしても壊せないケースがあります。
ただし、建築基準法の範囲内で適切に設計すれば、ツーバイフォー工法でもリフォームや間取り変更は可能です。
リフォームの自由度が低い傾向にある
ツーバイフォー工法は、在来工法のように柱や梁を残して大規模に間取りを変更することが難しい構造であるため、リフォームの自由度が低い傾向にあります。
リフォームやリノベーション自体は可能ですが、窓の拡張や壁の撤去といった工事は制約が多く、工期や費用もかさみやすいのが実情です。特に、耐力を担う壁を変更すると建物の強度低下につながる恐れがあるため注意しましょう。
箱型構造を基本とするため、変形地での設計自由度が低い点もデメリットの一つです。
構造体の建築コストを削れない
ツーバイフォー工法は、構造体の部材を変更するなどして、コストダウンできない点もデメリットの1つです。
建築基準法により、ツーバイフォー工法で使用できる部材は、JASまたはJIS規格をクリアしたものに限定されています。そのため、在来工法のように安価な材料に変更してコストを下げることは難しいでしょう。
一方、規格材は品質が均一で強度や耐久性が安定しているため、住宅の安全性や性能が確保されやすいのがメリットです。
そのおかげでツーバイフォー住宅は、一定水準以上の構造強度が保たれているともいえます。
ツーバイフォー工法(2×4)の施工事例
ここでは、TATTA!(グッドリビング)が実現したツーバイフォー工法(2×4)の施工事例をご紹介します。
- 回遊できるLDK空間のあるお家
- 太陽光で豊かに暮らす家
回遊できるLDK空間のあるお家

※出典:建築事例|浜松で注文住宅ならTATTA!|神奈川・岐阜・愛知でもワンプライス×注文住宅
ツーバイフォー住宅は、開口部が取りづらく間取りを制限されるケースがほとんどですが、この事例では、LDKから上階に上がる階段部に大きな吹き抜け空間を作っています。
上階から十分な日差しが入り、清潔感がさらに高まっているといえるでしょう。
ツーバイフォー工法特有の耐力壁を、キッチンとLDKをシェアするブラインド壁として利用し、開口部は対面キッチンをレイアウトしています。
さらに、LDKが回遊でき、階段を通じて上階とも行き来できる空間の演出は、ぜひとも参考にしたい実例です。
太陽光で豊かに暮らす家

※出典:建築事例|浜松で注文住宅ならTATTA!|神奈川・岐阜・愛知でもワンプライス×注文住宅
LDKを広い空間にするために、ツーバイフォー工法を選んだ事例です。
当初から広いリビングにしたいと考えている場合、構造のことも考えて耐力壁のレイアウトを事前に検討すれば、広々とした空間の演出も可能です。
大きなLDKでも構造柱などが残らないのは、ツーバイフォー工法ならではの特徴といえます。
ツーバイフォー工法(2×4)に関するよくある質問
ここでは、ツーバイフォー工法(2×4)に関するよくある質問に回答します。
- ツーバイフォー住宅は腐るって本当?
- ツーバイフォー工法の住宅は寒い?
- ツーバイフォー工法の住宅の寿命は何年?
ツーバイフォー住宅は腐るって本当?
ツーバイフォー住宅は比較的柱が腐りやすいといわれていますが、全ての住宅が該当するわけではありません。
ツーバイフォー住宅が腐りやすいなどのイメージは、木材として輸入材を使用しているケースによるものだといえます。
北米や東南アジアなど海外からの輸入材は、湿度の高い日本の気候に長時間晒されると劣化が進みやすいといわれています。
対策として、耐水性の高いヒバやヒノキ材を使用すれば腐りにくくなるでしょう。また、素材に含有されているヒノキオールとフェノール化合物により、シロアリ対策にもなるでしょう。
ツーバイフォー工法の住宅は寒い?
ツーバイフォー住宅は、寒い冬こそ真価を発揮します。
ツーバイフォー住宅のシェア率において北海道が全国第1位であることも、寒さに強いことを裏付けているといえるでしょう。
ツーバイフォー工法は、パネルを組み合わせるシンプルな構造であるため、隙間ができにくく高気密で断熱性の高い家づくりが実現できます。
ツーバイフォー工法の住宅の寿命は何年?
ツーバイフォー住宅に限らず、国内の木造住宅の取り壊し平均年数は約30年といわれています。
この数字は建物が使用できなくなる期限を示しているのではなく、あくまでライフスタイルの変化に応じて建て替える目安を示しているにすぎません。
定期的に適切なメンテナンスを施せば、50年以上快適に過ごすことも可能でしょう。
ツーバイフォー工法(2×4)で後悔しないためには
ツーバイフォー工法は高気密・高断熱であるため、冬でも夏でも快適に過ごせる工法です。
実現したい間取りのイメージができたら、ツーバイフォー工法を採用しているハウスメーカーや工務店に相談しましょう。
後悔しないツーバイフォー住宅を実現するためには、建築業者選びも重要な要素です。自分たちと相性が良く信頼性も高い建築業者を選びましょう。
TATTA!では、建物の面積に合わせてワンプライスで災害に強い、高気密・高断熱の暮らしを実現できる理想的な家づくりを提案いたします。
土地探しや資金計画、間取りの相談などに関心のある方は、ぜひお近くのTATTA!モデルルームにお越しください。